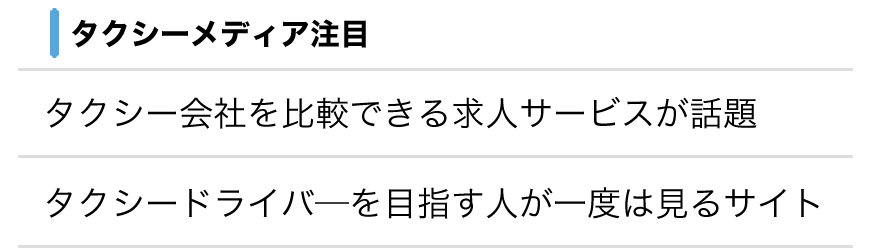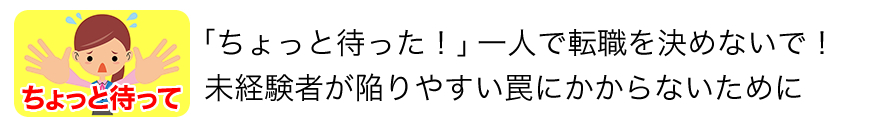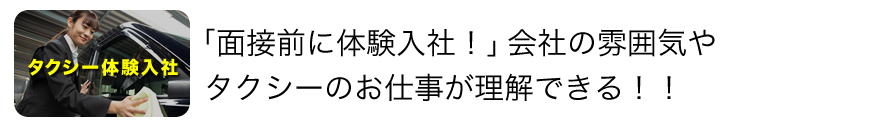見出し
【要注意】タクシー運転手も他人事ではない!煽り(あおり)運転のリスクと事故防止策とは?

近年、「煽り(あおり)運転」はドライブレコーダーの普及によってメディアでも頻繁に取り上げられることが増えました。
経験をされた事がある方はわかると思いますが、とても嫌な思いですよね。
この「煽り(あおり)運転」は他の車両に対して、①不必要に車間距離を詰める、②急な割り込み、③幅寄せ、④進路妨害などの危険な運転行為を指します。
これらは以前から常態化しており、事故やトラブルも生じていることもあって問題視されている許されざる行為です。

場合によっては一発免許取り消しもあります。
『煽り(あおり)運転』は当然、タクシー運転手にとっても無関係ではありません。
実はタクシーは仕事の特性上、多くの往来するクルマと関わるため、遭遇リスクが比較的高いのです。
タクシー運転手が被害者になるケース
タクシー運転手は、乗務時は必然と公道を拝借して仕事をする職業です。
そのためどうしても他の一般乗用車に比べますと『煽り(あおり)運転』などのトラブルに巻き込まれる確率も高くなってしまうことは否定できません。
▼特に以下における状況では、『煽り(あおり)運転』の被害に遭う事例が報告されています。
・渋滞や停車中に後方車に苛立たれるケース。
・齢者や酔客の送迎で急な停車が発生し、後続車に誤解されるケース。
・『道を譲らなかった』と因縁をつけられるケース(確率は非常に低いですが…)。
また、どうしてもタクシー車両は行灯や車体ボディの塗装などで一般車両と比較しても目立つことから、煽り(あおり)運転の標的になりやすいという側面もあるようです。

タクシー運転手が加害者とみなされるリスクも…
何度も言いますがタクシー運転手は、お客様を目的地まで安全・快適に送迎するプロフェッショナルのお仕事です。
しかしながら、時として運転態度やちょっとした言動が誤解を生むことで、加害者として扱われる危険性もあります。
▼たとえば以下のような行動は要注意ですので、気を付けましょう。
・乗り場での客待ちでタクシー停車中、割り込みと誤解されてしまった。
・急な割り込みにイラつき、軽くクラクションを鳴らした。
・追い越しの際、車間距離が近すぎた。
上記の内容は一見、些細な行動かもしれません。
しかし時として相手に「煽られた」と思わせてしまうリスクがあります…。
今のご時世、下手にSNSで晒されてしまったり、煽り運転と思わしき内容の映像を拡散されてしまった場合、該当のタクシー運転手はもちろん、タクシー事業者及び業界のイメージにも重大なダメージを与えかねません。
煽り運転を防止するためには?

タクシー運転手が煽り運転に遭わないことはもちろんですが、加害者にもなってはいけません。
そのためには、リスク回避のための「運転技術」と「心がけ」が必要になってくるのです。
ここでは具体的な対応策をまとめてみましたので、紹介しましょう。
常に余裕をもった車間距離
車同士の車間を詰めると、相手に威圧感を与えてしまい、煽りと誤解されることが多々あります。
速度に応じた十分な車間距離を保つことは、煽り運転防止だけでなく、事故防止にもつながります。
割り込みなどの懸念材料もありますが、車間距離を取ることは事故防止にも大変効果的ですし、今すぐにでも出来ますよ。
クラクションは極力使わないこと
教習所で習った方は覚えていますでしょうか?我が国の交通法規では現在、『クラクションは危険回避のため以外では原則使用してはいけない』ということになっていますよね。
クラクションは、道を譲ってくれたお礼の代わりに使用する方もいらっしゃいますが…基本は「警告」や「危険回避」で使用するものです。
正味気持ちのよいものではありません。
ですので下手にクラクションを使用してしまうと「怒っている」と相手に受け取られてしまう恐れがあるため、些細な場面では使わないよう注意が必要です。
ドライブレコーダーを前後に設置

ドライブレコーダー(以下:ドラレコ)は今現在、多くのタクシー事業者では搭載していると思います。
ここで敢えてお伝えするのもいかがなものかとも思いましたが、防犯上とても大切な事ですので敢えて記載したいと思います。
『煽り(あおり)運転』はもちろんのこと、乗車時に万が一のトラブルが発生した際、確固たる証拠がなければ加害者側に言い逃れをされてしまいます。
そうならない為にもタクシー車両は必ず前後方同時録画のドラレコを設置しているか確認しましょう。
おそらく多くのタクシー事業者は現在ドラレコは搭載していますが、一部のタクシー事業者では搭載していないという話を聞きます…。
この件に関しては不安であればタクシー転職時に会社説明会や面接にて質問してみると良いでしょう。

危険運転者には近づかない・関わらない
タクシー営業時の鉄則として、前方や後方、或いは左右斜めに走行する車両が蛇行運転や急な車線変更といった明らかに危険な走行をしている車両を見たら即座に距離を置くことを心がけましょう。
無理に関わろうとすると、不要なトラブルに発展する危険があります。
特に東京都内を例に挙げますと、連休中や土日などは普段運転をしない方がレンタカーを乗車されたり、都心部に不慣れな県外ナンバーの走行も目立ちます。
絶対に煽ったりせず、事故防止のためにも『近づかない』・『関わらない』という態勢を心がけてください。
タクシーの停車場所に配慮すること

タクシー営業中、お客様の乗降時に横断歩道や交差点付近に停車する際のあるあるで「他車の走行を妨げ、煽り運転を誘発する」という経験をお持ちのタクシー運転手の方はいらっしゃいませんか。
上記のトラブル回避は、お客様がタクシーをお降りになる前に一言「この先で停車してもよろしいですか?」と一声かけてみましょう。
それだけでも、悪質な煽り(あおり)運転をされずに済んだり、お客様とのトラブル防止につながっていきます。
タクシー事業者としての対策も不可欠
正味タクシー運転手個人の努力だけでは煽り(あおり)運転の被害を防止するには限界があります。
そのため、所属するタクシー事業者側も「煽り(あおり)運転対策の研修・設備投資」を行うことが望ましいでしょう。

もちろん運転手やお客様各々に事情があったりとそれに限った話ではないでしょうが、相手がいての運転。思いやりなくして運転は成立しないのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
煽り(あおり)運転は、いまや誰にでも起こり得る現代社会における交通のリスクです。
それらを許してはいけないのですが、おそらく人間が勝ち負けを好み追いかけ追いつくのを先天的に好む動物である以上は撲滅する気配はありません…。
しかし、タクシー運転手は運転のプロフェッショナルです。
日々さまざまな交通状況に直面するため、被害者にも加害者にもならないための意識と行動が不可欠です。
転職道.comでは、タクシー営業で必要不可欠な『安全運転』を第一に考えるタクシー事業者を、積極的に掲載しています。
ドラレコの全車完備はもちろん、不安を払拭するための定期的な安全運転の理解を深める研修及び安全教育の実施ななど…タクシー業界へ転職したい皆さんが安心して働ける会社をご提案します。
まずはお気軽に転職相談から始めてみませんか?