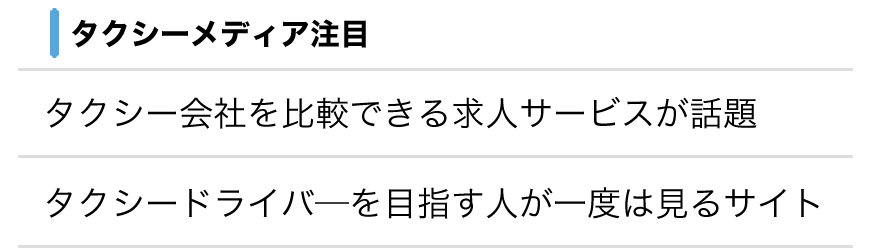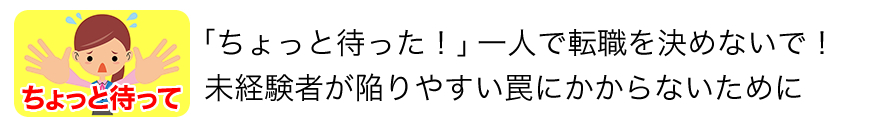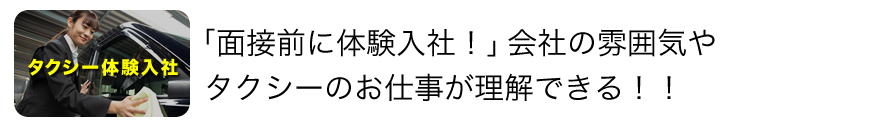見出し
タクシー運転での要注意!居眠り運転のリスクに備えよう【注意事項や回避方法を詳しく説明】

「春眠暁を覚えず」とはよく言ったものです。
春の暖かな陽気につい寒さに応えた身も心も陽の長さや気温に慣れず、眠気が襲ってくることもしばしばあるのがこの春先から初夏にかけてのシーズンです。
しかしながら、それは同時に交通事故が増加するシーズンでもあるのです。
今回は居眠り運転のリスクと回避方法をお伝えします。前半はシビアですが、後半は回避する方法も記載していますので、どうぞ最後までご覧になっていただけますと大変うれしく思います。
今日も一日、ご安全に!
居眠り運転のリスクって?

とりわけタクシー運転手として働くうえで、最も気をつけたいのがこの「居眠り運転」です。
「居眠り運転」は強烈な眠気によって運転中に意識が朦朧(もうろう)として重大事故を引き起こすため、どんなことがあっても回避しなくてはいけません。
実車・回送に関わらずタクシーの長時間運転、深夜帯の勤務や不規則な生活リズムなどが休憩や睡眠をうまく取れずにコントロールできない状況が重なると、一瞬の油断の隙に重大な事故を引き起こすリスクがあります。

「うっかり」では済まされない事案
居眠り運転は単なる「うっかり」では済まされません。
意識が飛んでいる状態で車を操作すれば、自分自身はもちろん、乗車中のお客様、そして他の歩行者やドライバーにも危険が及びますよね。
これは職業ドライバーとしての信頼にも大きく影響します…。
重大な事故に繋がる
居眠り運転の最も深刻なリスクは「重大事故の発生」です。
過去の事例を見ても、居眠りによる追突事故や歩行者との接触事故が後を絶ちません。
ほんの数秒の油断が、信号無視や車線オーバーといった致命的なミスに繋がる可能性が非常に高いのです。
あえて厳しいことを言いますが、物損もそうですが万が一人身事故を起こしてしまえば、運転手個人の責任だけではなく、会社全体の信用問題にも波及します。
最悪の場合損害賠償や免許停止など、キャリアを脅かすリスクも現実として存在するのです。

実車時はお客様に多大な迷惑も
居眠り運転のタイミングがもし空車ではなく「実車中」であれば、その影響はさらに重大です。
お客様はタクシーを安全な移動手段として利用しているにもかかわらず、命を守るタクシー運転手が居眠りによって不安を与えてしまっては、サービス業としての信頼を大きく損なうことになります。
万が一事故に遭えば、タクシー運転手だけでなくお客様ケガを負います。
またそれだけでなく、精神的なショックも与えてしまう可能性があります。
乗車後の口コミや評判により、営業成績などにも悪影響が出る可能性も否定できません。
相手がいた場合の損害は大きい
もし居眠り運転における事故の際に、相手がいた場合はどうなるでしょうか?
この場合も金額は前後あるものの損害賠償は非常に高額になる可能性があります。
例えば車両同士の事故でも、営業車や高級車との接触で高額請求が発生することもありますし、無論相手が歩行者であれば人身事故となります。
万一後遺症が残れば賠償金は数千万円にも及ぶこともあるので用心しましょう。
また、居眠りが原因であると判明すれば、過失割合も不利になります。
保険の等級が下がるだけでなく、会社からの処分や解雇に繋がる場合もあり、運転手としての人生設計にも大きな影響を及ぼします。
居眠り運転をしないために
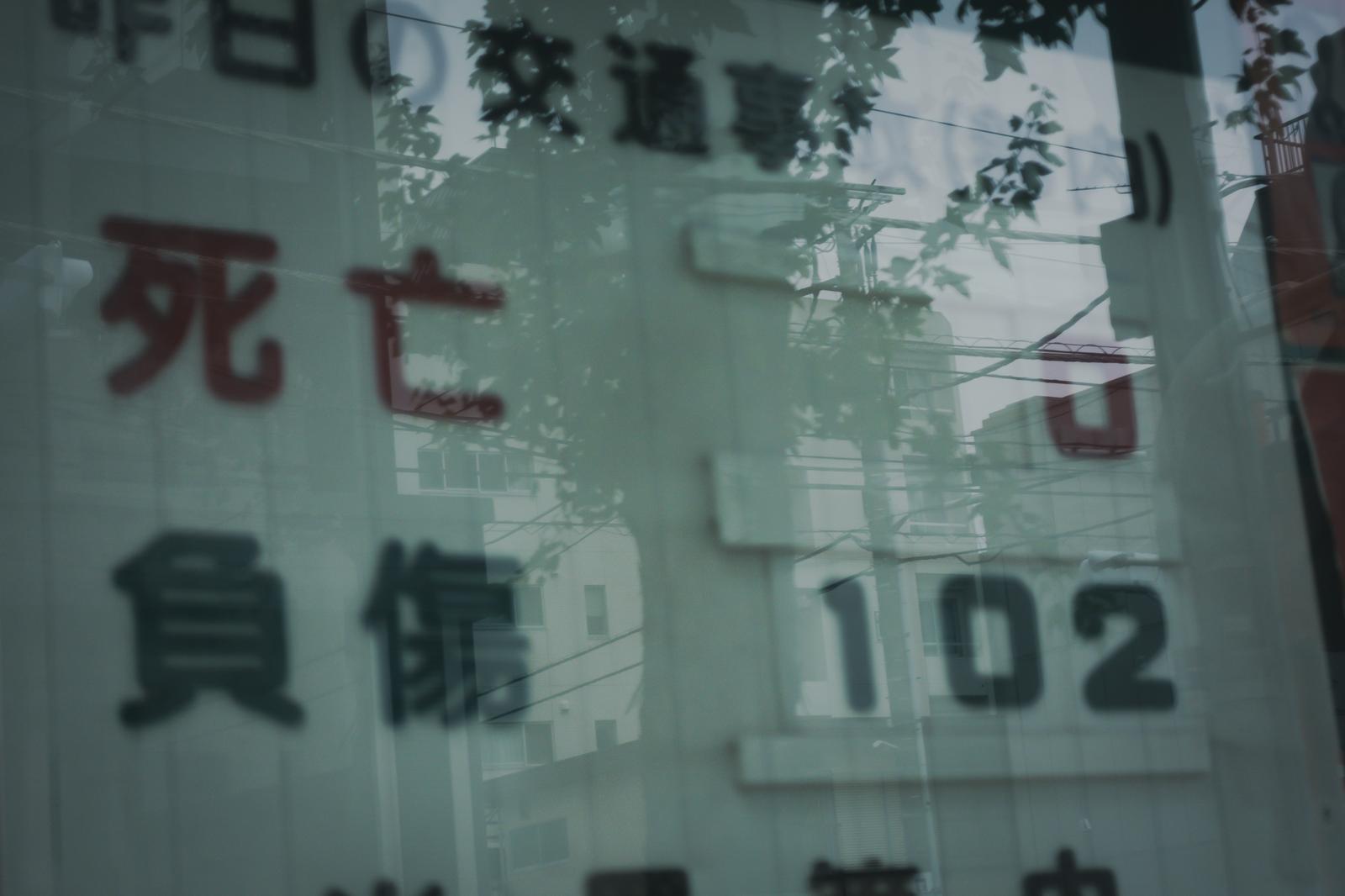
ここまでかなりシビアな内容でしたが、あえて「ご安心ください」という内容にはまとめません。
ただし、今回の「居眠り運転」はタクシー運転手自らが回避することが可能な事象です。
それをこれからお伝えしましょう。
絶対に安全運転で1乗務を無事に終わるために、しっかりと一読して頂けたら嬉しい限りです。
充分な睡眠を取る
何よりも重要なのは「質の高い睡眠」です。
よく言われているのは「毎日最低でも6〜7時間の睡眠を確保する」ことが基本のようですが、それだけでは足りないこともあります。
仮眠や昼寝を上手く取り入れて、こまめに休息をとることが居眠り防止に直結します。
隔日勤務の明けは、自由時間ではありますが上手に計画的に過ごしましょう。

例えば『就寝前のスマホ使用を控える』、『寝室の環境を整える』など、睡眠の“質”にこだわる努力を少しずつでも良いのでしてみましょう。
休憩をしっかりと取る
タクシー運転手は長時間運転をする職業ですが、連続して運転を続けるのではあまりお勧めしません。
出来れば2〜3時間に1回は短い休憩を挟むのが理想的とも言われています。
言わば「一日中座りっぱなし」がほとんどですので、空いた時間に仮眠+ストレッチや深呼吸もしてみてはいかがでしょうか。
仮眠が取れる環境であれば、15〜30分の俗に言う「パワーナップ」も効果的です。
また、お気に入りの休憩スポットはもちろん、会社の駐車場・仮眠室をうまく利用しましょう。

個人的に成田空港や千葉方面送迎の帰りは市川PAがおススメで、横浜方面の帰りは第三京浜の玉川料金所の小さいPAも良いですよ。
深酒をしない
アルコールは睡眠の質を下げるだけでなく、翌日に強い眠気や倦怠感を残します。
…いや、いいんですよ。お酒は美味しいですし楽しい。楽しくほどほどにを推奨します。
あくまでここでお伝えしたいのは「前夜に飲みすぎたせいで眠気が抜けない」といった状況は、居眠り運転のリスクを高める典型的な原因に繋がるということです。

健康管理の一環として、仕事前日はなるべく飲酒を控えるよう意識しましょう。
特に二日酔い状態での運転は判断力も鈍るため、事故のリスクが急増します。
お風呂に浸かる
お風呂に浸かる…つまり入浴には自律神経を整える効果があります。
ぬるめのお風呂にゆっくり浸かることで、リラックスし、睡眠の質が高まるとされています。
シャワーだけで済ませがちな日々でも、できるだけ湯船に浸かる習慣をつけることで、身体の回復力もアップします。

「うぉぉぉ~…」と声が出るくらいに気持ちよかったらリフレッシュしている証拠でしょう笑。
筆者が所属するタクシー事業者でも出番会で毎回お風呂で疲れを取りましょうと推奨するくらいですよ♪
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の場合

『ぐぅぉぉぉおおおおおおあ~×5…ぐぅアッ…!!!!!プぅ~…』
なんていびきをかいていたら、要注意です。
それは、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の疑いが強いかもしれません。
原因は遺伝だの骨格だの、そして肥満だのと諸説ありますが、医学的な見解は専門外ですのでここでは避けさせてください。
しかし、知り合いやパートナー、家族に指摘されて分かったケースが多く放置しておくと糖尿病、心臓発作、心不全、脳卒中、心房細動、不整脈の発症リスクも上昇すると言われています。
タクシー運転手も実際、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の疑いがある方や、治療中の方の割合は非常に多く、タクシー事業者も対策に積極的な動きを見せています。
例えば東京大手のタクシー事業者「日の丸交通」では平成28年に、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検診サポートを開始しております。
また、東京大手四社の「日本交通」と「大和自動車交通」も令和5年に国内大手電機メーカーNECと共同で、タクシー運転手の健康状態や運転状況を可視化するため、運行管理の高度化に向けた実証を行っています。
早期の検診
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の症状は、睡眠中に呼吸が一時的に止まることで、脳が深く休めず、慢性的な眠気や集中力低下を引き起こすのです。
周囲の助言によって発覚することが多く、最初は本人の自覚がないことが多いのです。
もし『いびきがひどい』、『寝起きがしんどい』または『日中の眠気が強い』というタクシー運転手や、これからタクシー業界に転職を考えている方がいらっしゃいましたら医療機関での検査を受けることをおすすめします。

「ブラックブラックガムが手放せない」
「レッドブル2缶飲まないとやっていけない(結構危険)」
以上のタクシー運転手(これから転職をされる方も含む)は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)を疑った方がいいかもしれません…。
改善に向けた治療の導入
睡眠時無呼吸症候群の治療は、検査を実施し、数値で基準値を超えていた場合は持続陽圧呼吸療法(CPAP)などの機器を使う方法が一般的となっています。
症状が改善されれば、眠気の軽減だけでなく、集中力や判断力の向上にも繋がり仕事もはかどるのではないでしょうか。
タクシー運転手として長く働くためにも、自分の体調と向き合い、早期発見・早期治療が安全運転の大前提となります。

ほどんどの皆さんが「改善された」「良くなった」「家族には寝てる時のフォルムに驚かされた笑」という声を聞きますよ。
【注:本内容は個人的な感想の一例であり、医学的な内容ではないのと、100%効果を保証するものではありません。】
健康第一が安全第一を生む
タクシー運転手の仕事は、お客様を目的地まで安全かつ快適に運ぶ「プロの運送・接客サービス業」です。
そして、その基盤にあるのは「健康管理」です!
居眠り運転の防止は単なる個人の努力だけでなく、職業意識と責任感の表れでもあるのです。
これからタクシー業界に転職を考えている方も、タクシー運転手として長く働き続けるためには、ご自身の体調管理を万全に整える意識を普段から持つこと…これが何より重要と言えるのではないでしょうか。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
タクシー運転手として働く上で、居眠り運転のリスクは常に意識しておくべき重要なテーマです。
事故のリスクを未然に防ぐためにも、日々の健康管理を怠らず、規則正しい生活を送ることが不可欠なのです。
眠気というのはまさに『見えない敵』ですが、防ぐ手段はたくさんあります。
充分な睡眠とこまめな休憩、飲酒の制限、そして睡眠時無呼吸症候群(SAS)など必要なら医療機関での検診(※ここでは睡眠障害などは割愛します)…これらを積み重ね実施することが、タクシー業界における安全と信頼を築いていきます。
これからタクシー転職を考えている方も、今タクシー業界で働いている方も、自分自身の身体と向き合い、「安全第一」を実現しましょう。
そしてお客様の命を預かるという誇りを胸に、今日も安全運転を心がけていきましょう。
タクシー業界に興味はあるけれど、「体力面」や「健康管理」が不安な方も多いはず。
転職道.comでは、無理のないシフト管理と休憩制度、健康診断制度を整え、安心して長く働けるタクシー会社の情報を一流のカウンセラーがご提案します!
まずはお気軽に転職相談から始めてみませんか?