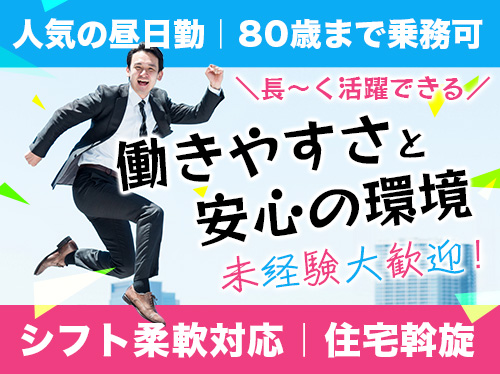大都市では交通空白人口、増加中!
 いつもタクシーをご利用いただき誠に有難うございます。
いつもタクシーをご利用いただき誠に有難うございます。このブログの写真は、友ケ島で撮ったものです。紀淡海峡に浮かぶ4つの島を総称して友ケ島と呼びます。この島は明治時代から第二次世界大戦が終わるまで軍事要塞として使用されていました。写真の風景、第3砲台跡付近のものですが、まさにThe Last of Usのゲームの世界にタイムトリップしたかのようでした。
ブログタイトル、大都市では交通空白人口が増えているという現実があります。鉄道駅から半径800m、デマンドバスやコミュニティーバスを含むバス停留所から、半径300mの範囲外にある地域を「交通空白地」と呼び、それは大都市においても、多数存在しています。それらの地域で活躍するのがタクシーです。
全国の交通空白地における人口は毎年減少傾向にあり、2020年には2500万人でした。これは2010と比べて8%の減少です。なぜなら、過疎地から都市部へ人口が移動しているからであり、国内の総人口の減少(10年間で1.8%減少中)とは別に考えなければなりません。
例えば大阪府堺市における交通空白地域における人口が顕著に増えています。堺市ではこの10年間でバス停留所が約2割減りました(現在約500箇所)先日8月2日、大阪タクシー協会がイベント開催した「ららポート堺」も住所では美原区黒山です。美原地区では大規模な住宅開発が進んだ結果、このような大規模ショッピングセンターもできたわけです。多くの新婚さんたちが移住したものと思います。将来子どもたちが独立して自家用車も手放すとなると「移動の確保」が日常生活の問題となってきます。堺市を例に出しましたが、大阪市、豊中市、八尾市、松原市でも同様の現象は起きています。
鉄道・バスが使いづらい場所ではタクシーを使うわけですが、2023年に富田林市の金剛バスが廃止されたようにバスも便数を減らしたり最終便の時間を前倒しにする傾向にあります。近鉄バスでは大阪・京都府エリアで平日に運行する路線バスの便数は約3100本ですが、これはコロナ禍前と比べて約2割少ないです。
バス会社の経営者は「生産年齢人口のこのようなペースで減少するなか、運賃収入が原資の民間バスだけでは支えられない地域はこれからも増えていく。自治体は自分ところの公共交通データを把握し、地域内事業者と連携しなければならない。欧州で自治体が公共交通計画を策定・運用しているように」と言います。
タクシーの役割を強く認識せざるを得ないニュースです。
お読みいただきありがとうございます。
この求人に応募する
- ※掲載情報についての詳細は、必ず各掲載企業へご確認ください。